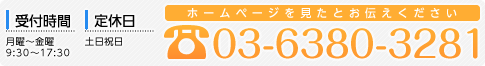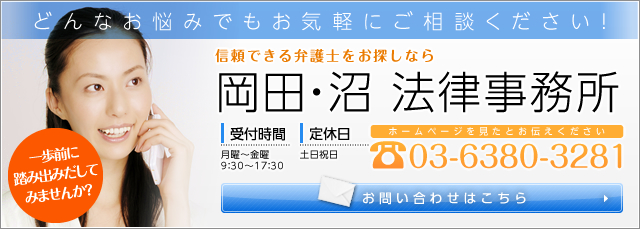刑事事件
2013年4月 2日 火曜日
釈放されるタイミング
逮捕された被疑者はもちろん、被疑者の家族にとって、いつまで身柄拘束が続くのか、釈放されるとすればそれはいつなのかということは重大な関心事です。今回のブログでは、標準的な刑事手続の流れと、被疑者・被告人がどのタイミングで釈放されることがあり得るかについてご説明させていただきたいと思います。
1.逮捕・送検
警察による逮捕がなされると警察官による取調べがなされ、逮捕から48時間以内に 検察庁に事件が送られます(これを送検と言います)。
2.勾留請求
送検されると、検察官は簡単な取調べを行い、送検から24時間以内に勾留(原則と して10日間の身柄拘束)請求するか否かを決定します。検察官が勾留請求しない場合には、被疑者は釈放されることになります。
この送検後、検察官の勾留請求前の弁護人の活動としては、例えば、早期に被害者と 示談が成立する予定がある、あるいは示談が成立したなどの事実を証拠とともに示して、検察官に勾留請求しないよう申入れを行います。その結果、検察官が勾留請求せず、被疑者が釈放されることがあります。当事務所で担当した事件でも、この段階で被疑者が釈放されたケースがあります。
3.勾留質問・勾留決定段階
検察官が勾留請求すると、裁判官が被疑者に勾留質問を行い、被疑者を勾留するか否 かを決定します。裁判官が勾留請求を却下した場合は、被疑者は釈放されることになります。
当事務所で扱ったケースでも、受任後、勾留質問前に裁判所に意見書を提出して裁判官に面会を求め、その結果、検察官の勾留請求が却下され、被疑者が釈放されたケースがあります。
4.勾留段階
裁判官が勾留を認めると、被疑者はその後原則として10日間(勾留延長されるとさらに原則として10日間、合計20日間)身柄拘束されることになります。
この段階での弁護人の活動としては、不当な勾留に対して準抗告を申し立てることが 考えられます。勾留の必要性がない場合など、不当な勾留であると裁判所が認めた場合には、被疑者は釈放されることになります。
5.検察官による終局処分段階
勾留満期までに、検察官は被疑者を裁判所に起訴するか不起訴にするかを決定します 。起訴されると、その後、事件は裁判所で審理されることになり、不起訴になった場合 には被疑者は釈放されることになります。
この段階でも、弁護人は、これまでの弁護活動の結果を前提に、検察官に不起訴、あ るいは、起訴される場合でも、より軽い略式起訴(罰金刑)となるよう検察官と交渉を行います。当事務所が扱ったケースでも、不起訴あるいは略式起訴によって、被疑者が勾留満期までに釈放されたケースが多数あります。
6.起訴後
これらの弁護活動が奏功せず、起訴(公判請求)された場合には、公判(裁判)まで 引き続き身柄拘束が継続することになります(被告人勾留)。
しかし、この段階からは、裁判所に対して保釈請求をすることが可能になります。保 釈が認められるためには、証拠隠滅のおそれがないことや保釈保証金の納付(東京地裁では150万円~200万円程度が下限になります)などの要件を満たす必要がありますが、被告人勾留は起訴前(被疑者段階の勾留)より長期間の身柄拘束になりますので、要件を満たすことが可能な被告人については、できるだけ保釈請求を検討すべきでしょう。
当事務所でも、保釈請求を行ったケースでは、ほとんどの場合、保釈が認められてお ります。
7.公判(裁判)
保釈請求ができず、公判に至った場合、無罪判決がなされれば釈放されるのは当然で す。他方、自白事件など、有罪が争えない場合には、執行猶予付きの判決を目指すことになります。
判決で執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、被告人は釈放され、執行猶予期間中、 何事もなく過ごした場合には、刑の言い渡しは効力を失うため、結局、刑の執行を受けることはなくなります。例えば、懲役1年6月、執行猶予3年という判決を受けた場合、刑の確定後3年、他の犯罪を犯すことなく経過すると、懲役1年6月という刑の言渡 しの効力がなくなるので、刑務所に行かなくてもすむのです。
初犯の場合、多くは執行猶予付き有罪判決となると言われておりますが、犯罪行為の 内容や、被害の程度などによっては執行猶予が困難なケースもあります。また、犯した 犯罪自体は比較的軽微でも、全く反省の情が窺えない場合などでは、初犯での実刑判決も考えられます。
したがって、事前に執行猶予を目指す公判での具体的戦略を練ることが極めて重要と 言えます。
このように、刑事手続の各段階によって、被疑者・被告人の身柄解放を目指す活動は異なります。また、早期の身柄解放だけではなく、最終的な公判段階で、執行猶予を目指す具体的戦略を早期に練る必要もあります。そのため、家族が身柄拘束を受けた場合には、なるべく早期に弁護人を選任した方が良いと言えるでしょう。
1.逮捕・送検
警察による逮捕がなされると警察官による取調べがなされ、逮捕から48時間以内に 検察庁に事件が送られます(これを送検と言います)。
2.勾留請求
送検されると、検察官は簡単な取調べを行い、送検から24時間以内に勾留(原則と して10日間の身柄拘束)請求するか否かを決定します。検察官が勾留請求しない場合には、被疑者は釈放されることになります。
この送検後、検察官の勾留請求前の弁護人の活動としては、例えば、早期に被害者と 示談が成立する予定がある、あるいは示談が成立したなどの事実を証拠とともに示して、検察官に勾留請求しないよう申入れを行います。その結果、検察官が勾留請求せず、被疑者が釈放されることがあります。当事務所で担当した事件でも、この段階で被疑者が釈放されたケースがあります。
3.勾留質問・勾留決定段階
検察官が勾留請求すると、裁判官が被疑者に勾留質問を行い、被疑者を勾留するか否 かを決定します。裁判官が勾留請求を却下した場合は、被疑者は釈放されることになります。
当事務所で扱ったケースでも、受任後、勾留質問前に裁判所に意見書を提出して裁判官に面会を求め、その結果、検察官の勾留請求が却下され、被疑者が釈放されたケースがあります。
4.勾留段階
裁判官が勾留を認めると、被疑者はその後原則として10日間(勾留延長されるとさらに原則として10日間、合計20日間)身柄拘束されることになります。
この段階での弁護人の活動としては、不当な勾留に対して準抗告を申し立てることが 考えられます。勾留の必要性がない場合など、不当な勾留であると裁判所が認めた場合には、被疑者は釈放されることになります。
5.検察官による終局処分段階
勾留満期までに、検察官は被疑者を裁判所に起訴するか不起訴にするかを決定します 。起訴されると、その後、事件は裁判所で審理されることになり、不起訴になった場合 には被疑者は釈放されることになります。
この段階でも、弁護人は、これまでの弁護活動の結果を前提に、検察官に不起訴、あ るいは、起訴される場合でも、より軽い略式起訴(罰金刑)となるよう検察官と交渉を行います。当事務所が扱ったケースでも、不起訴あるいは略式起訴によって、被疑者が勾留満期までに釈放されたケースが多数あります。
6.起訴後
これらの弁護活動が奏功せず、起訴(公判請求)された場合には、公判(裁判)まで 引き続き身柄拘束が継続することになります(被告人勾留)。
しかし、この段階からは、裁判所に対して保釈請求をすることが可能になります。保 釈が認められるためには、証拠隠滅のおそれがないことや保釈保証金の納付(東京地裁では150万円~200万円程度が下限になります)などの要件を満たす必要がありますが、被告人勾留は起訴前(被疑者段階の勾留)より長期間の身柄拘束になりますので、要件を満たすことが可能な被告人については、できるだけ保釈請求を検討すべきでしょう。
当事務所でも、保釈請求を行ったケースでは、ほとんどの場合、保釈が認められてお ります。
7.公判(裁判)
保釈請求ができず、公判に至った場合、無罪判決がなされれば釈放されるのは当然で す。他方、自白事件など、有罪が争えない場合には、執行猶予付きの判決を目指すことになります。
判決で執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、被告人は釈放され、執行猶予期間中、 何事もなく過ごした場合には、刑の言い渡しは効力を失うため、結局、刑の執行を受けることはなくなります。例えば、懲役1年6月、執行猶予3年という判決を受けた場合、刑の確定後3年、他の犯罪を犯すことなく経過すると、懲役1年6月という刑の言渡 しの効力がなくなるので、刑務所に行かなくてもすむのです。
初犯の場合、多くは執行猶予付き有罪判決となると言われておりますが、犯罪行為の 内容や、被害の程度などによっては執行猶予が困難なケースもあります。また、犯した 犯罪自体は比較的軽微でも、全く反省の情が窺えない場合などでは、初犯での実刑判決も考えられます。
したがって、事前に執行猶予を目指す公判での具体的戦略を練ることが極めて重要と 言えます。
このように、刑事手続の各段階によって、被疑者・被告人の身柄解放を目指す活動は異なります。また、早期の身柄解放だけではなく、最終的な公判段階で、執行猶予を目指す具体的戦略を早期に練る必要もあります。そのため、家族が身柄拘束を受けた場合には、なるべく早期に弁護人を選任した方が良いと言えるでしょう。
投稿者 岡田・沼法律事務所